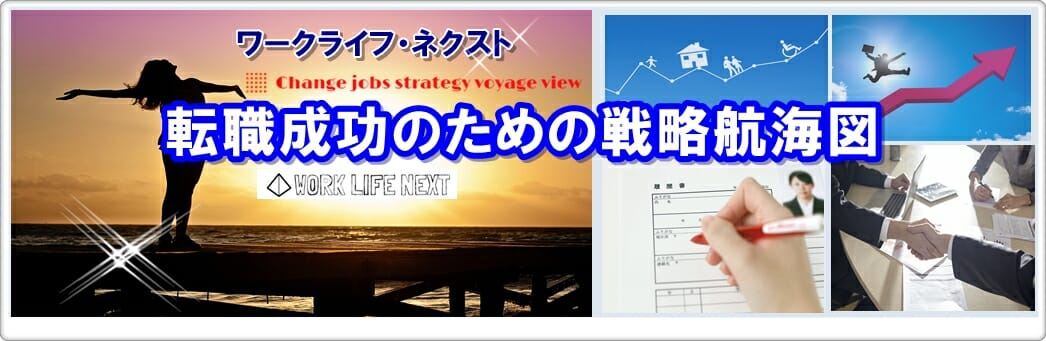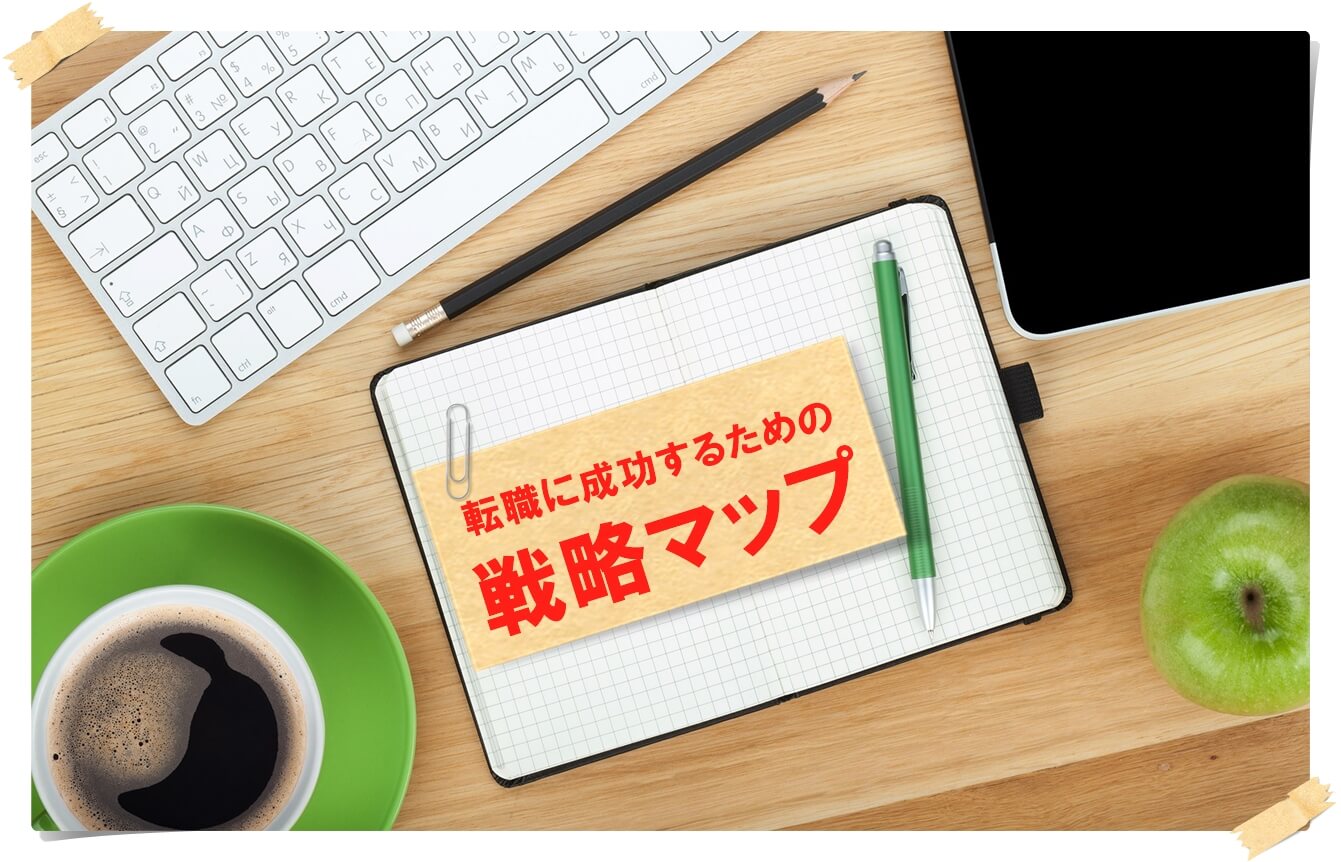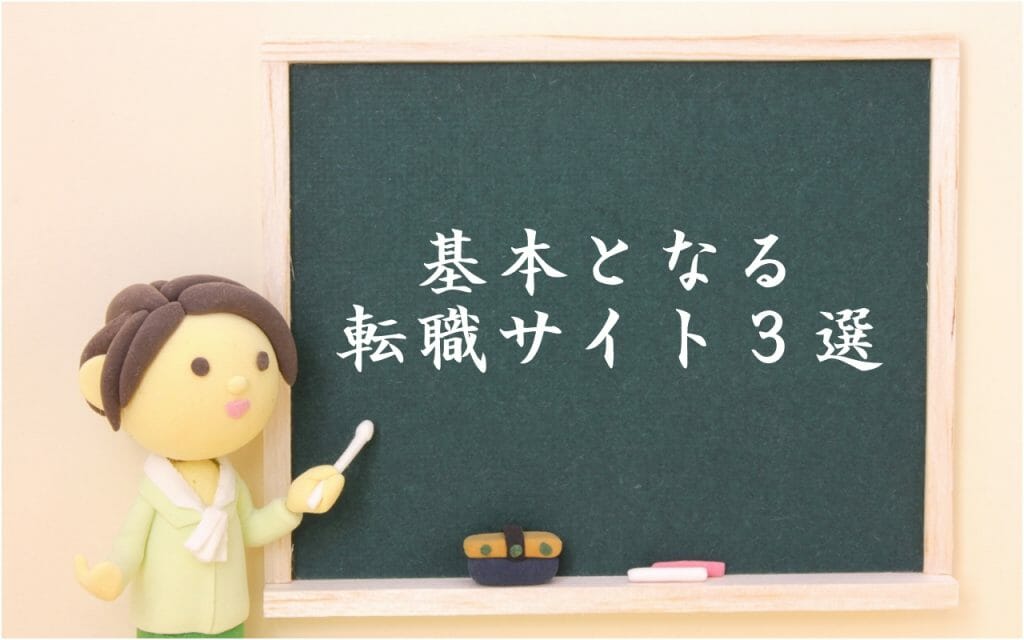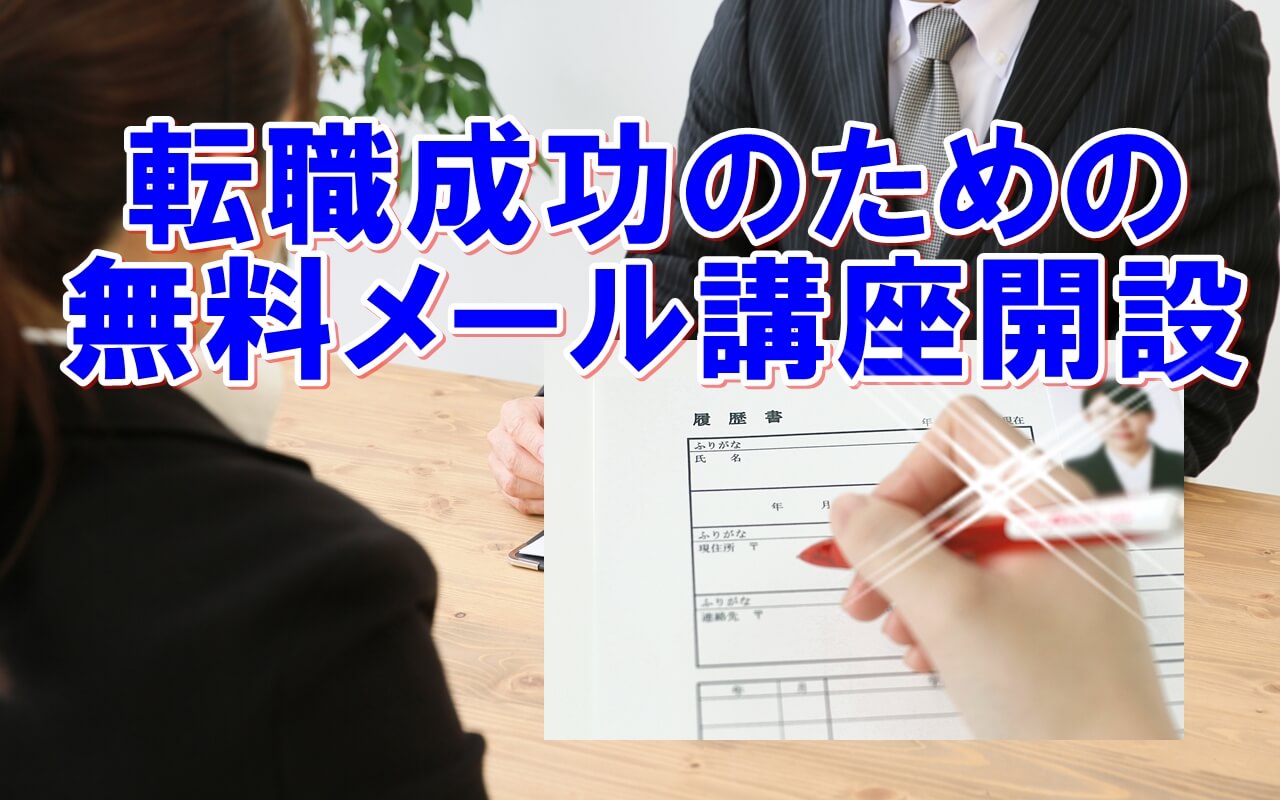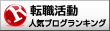この記事は、30代以上で部下を持つミドルクラスのビジネスマン向けの内容です。
これから、新たなステージへの転職を考えているも今の職場で働くにしても、価値観の違う若手メンバーを率い、組織マネジメントするケースも多くなってきますよね。
ですから、必ず留意しておかなければならない重要なことです。
さて、突然ですが、あなたには、部下がいますか?
もし、いる場合、部下に対しどのような接し方をしていますか?
これは、私が経験したことで、今でも常に肝に命じていることを書きますね!
目次
自分と他人は、そもそも違う生き物である

自分にとっての大事なことでも、相手にはどうでもいいことって、あるんですよね。
相手の興味、ニーズに合っていないにもかかわらず、自分が価値を感じている事を良かれと思い、薦めるといった行為が、逆に相手には、ストレスになるケースがあるのです。
例えば、自分があるビジネス書を読んだとします。自分にとっては、とても有益な内容でした。
ものすごくためになったから、良かれと思い、会社で自分の部下に読むように薦めたとします。
ところが、部下はその本を手に取ったものの読んでいないようです。
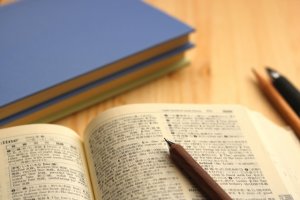
ある日、「あの本、まだ読んでいないのか?」
「お前のためを思って、お前に役立つ本を教えてやってんだよ。」
「なんで読んでないの? だからお前は駄目なんだよ!」と。
自分が抱えている問題や興味を持つ分野に対して、参考になる本と、部下が参考にすべき本は必ずしも一致するとは限りません。
だから、軽く薦める行為は問題なくても、強制的な行為はやり過ぎといったことになるのです。
これは、たまたま本の事例ですが、ビジネスの現場では、このようなシーンは、少なくないですよね。
自分のやり方が正しいとは限らない

例えば、自分の仕事のやり方を部下に伝えたとします。
しかし、その部下は、いつになってもそれができずにいます。
そうすると「どうして、お前はできないの?」となります。
これはよくある話ですね。
ただし、それはあくまで、自分独特のやり方である場合も多く、相手にとっては、理解しにくく、本人としては合わないことだってあるわけです。
そこをきちんと紐解き、その他のアプローチを試してみようともせずに、「こいつはダメだ!」と決めつけるのは、少々傲慢な気がしませんか?
相手によかれを思っても、無理強いはNG!

ここで重要なのは、自分としては、相手に対し良かれと思って起こす行動が相手にとっては、弊害はあっても、何のメリットもない場合です。
特に、ビジネスの現場における「教育」「トレーニング」の場合、そのメンバーたちの成果や成長につながらないなどの事態にも陥ってしまうから、話はやっかいなのです。
指導、教育という大義名分のもとに自分の価値観や成功体験をベースに、部下に自分の考えをゴリ押ししてませんか?
相手の特徴に合わせたアプローチができていないにもかかららず、その部下の能力のせいにしていませんか?
昨今は、正社員の流動化が激しく、転職するのも当たり前の時代になりましたので、転職業界は儲かります。
しかし、よく考えるべきことは、人を辞めさせる以前に、会社として、上司として、しかるべき教育ができているのでしょうか?

特にプレイングマネージャーの立場に人などは、自分の売上、数字で手一杯で、部下の悩みに対し、真摯に向き合えているのでしょうか?
向き合っているつもりが、独りよがりな対応になってしまい、不必要にダメージばかり与えていないでしょうか?
ひとりよがりの指導は、
相手のためにならず、
ただの自己満足

要は、一見、相手のためを思っているようでも、相手にとってはためにならないケースが非常に多いのです。
会社組織には、いろいろなタイプの人がいて、出身地も違えば、当然、価値観も異なります。
しかし、会社が目指す方向性、目標があり、そこで働く従業員はベクトルを合わせる必要があるのは、言うまでもありませんよね!
だからころ、上司、部下の信頼関係は必須だと思うのです。
さて、人を理解することは、非常に難しいのです。
しかし、相手の理解は、信頼関係を作るための重要なポイントなのです。
ある人にとっては一大事であっても、他人にとっては些細なこともあるのです。
だから、信頼関係を築くためには、相手にとって大切なことは何なのかを把握し、それをあなたも大切に思うことも必要なシーンがあるのではないでしょうか?
もちろん、価値観は人によって異なるので、「大切に思うこと=自分が相手と同じ価値を感じなさい」ということではありません。
『相手が価値を感じていることをバカにしたりせずに、仮に自分が理解できなくても、敬意を払う』といった方が、わかりやすいかもしれません。
自分の経験、ノウハウはの
押し付けは相手が迷惑

人は自分の経験に照らし合わせてみて、自分は他人のニーズや欲求がわかっていると思い込んでしまうことがあります。
つまり、他人の行動や考え方を自分の考えや常識を通して、解釈してしまいやすいので、その解釈そのものが間違っていることが、非常に多いわけです。
それに気づかず、人に接してしまうのです。
例えば、40代の上司が20代の部下に指導をする際、自分が20代だった頃を忘れ、今の自分の経験をもとにした価値観を部下に押し付けてしまうことなどは、よくありがちなこと。
指導、教育といった大義面分の元に、自分本意な態度になっていないでしょうか?
自分が20代の頃に、今と同じ考え方で物事に対処できていたかをよーく思い出してみる必要がありますね。
私の場合は、それを忘れてしまっていました。
今の自分の価値観は20年以上培ってきた経験から至ったもので、それを今の20代の若者に、押し付けるのは、ナンセンスなのです。
しかも、20年前と今では、世の中の環境も変わり、常識だって変化していますから。
世代間ギャップを把握して、
発言をしていますか?

当然、若い人の考え方も違うはずですよね。
だから、自分の言葉を押し付けるのではなく、耳を傾ける努力が必要なのでしょう。
相手の育った環境や、時代背景がその人の物事の考え方にどう影響を及ぼしているのかなどを少し観察してみるのもよいのではないでしょうか?
人はそれぞれなので、その考え方、価値観をできるだけ理解した上での、接し方を心掛けること。
そこのギャップを理解しないままの発言、行動は控えるべきです。
あなたがミドルマネジメント層として、転職をする際に、ここは非常に重要な部分となります。
それが、公平に人に接することにつながるのだと思います。
あなたは、どう思われますか?



- 【PR】組織やチームで人を動かすために必要なこととは?
トライブ=人を動かす5つの原則(著者:デイヴ・ローガン他)
★★★★★ “マネジメントに携わる人の必読書”